断食4日目!~毎年恒例のお盆一週間断食45回目
私にとって断食は“修行”でなく“道楽&健康管理”です。
ふだんの暴飲暴食の罪滅ぼしに内臓を休ませてあげます。
今朝の体重は
減食2日間+断食3日で、2.0 Kg 減。
とても元気、快調です。
☆朝夕2回、金魚運動・毛管運動・合掌合蹠運動。
詳しくは以下をご覧ください。
・西式健康法の6大法則
・らくらく毛管運動
http://www.iweekly.jp/file/rakuraku_mao_guan_yun_dong.html
・毛管運動の動画
http://video.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%AF%9B%E7%AE%A1%E9%81%8B%E5%8B%95
☆
【易経一日一言】や講演・セミナーのお知らせは
別に書いてます。
↓
土壌づくりの時代/わからないままに受け止める/
継続は力なり~帝王学の書~8月7日の易経一日一言
☆
「8/2,3日の減食2日間を経て8/4~10の一週間断食 」
☆『人参の絞り汁』を昼と夕の2回。
今回は初めて酵素とハーブティを取り入れてみた。
水は1日3リットル以上。
昨年初めて使った、KOBOジュースを朝1回。
☆朝夕、金魚運動・毛管運動・合掌合蹠運動。
☆毎日2~3回の水風呂。
☆洗腸を1回。
☆散歩は涼しい時間帯に。
☆マリンマグ(粉)(副作用のない瀉下剤)朝晩に飲用。
断食は身体の大掃除です。
栄養吸収がないため腸の働きがおちるので
緩下剤で補助し、水分の補給が必要です。
一般的な下剤は化学物質を含むので断食中には使用出来ません。
スイマグやマリンマグは生薬で粘膜の傷も治します。
緩やかな作用の下剤なので断食中も害はありません。
また一日一回の洗腸は水分補給も兼て、楽になります。
※大昔は西式やヨガ他、数か所の断食道場を巡りました。
25年以上前から、自宅で工夫しながらやってます。
水を飲むだけの「本断食」も昔は数回やりました。
『果物の絞り汁』『寒天断食』『スマシ汁断食』…etc.
今年は『人参ジュース&酵素&ハーブティ』断食です。
☆
【玄米食と断食は、惜福の工夫】
5歳の頃、家のごはんが玄米になった。
亡・二木謙三先生の指導だった。
病気がちだった家族が 健康になった。
それ以降の 父の人生は 亡くなるまで
「玄米食普及」と「世界連邦」 だった。
【惜福の工夫】とは、
易経を座右の書としていた幸田露伴が
『努力論』のなかで薦めているもので、
幸いをあとに残しておいたり、人に分け与えたりして、
わざと不足の部分を作り出すことです。
易経的な考えでは、
いつもいつも得するほうを選択しないこと、
時に損をしてあえて満ち足りないようにすることです。
損とは譲るということでもありますが、
これは見返りなく譲るということです。
これぞまさしく陰の力、陰徳なのです。
父が玄米食運動家だった関係で、私の幼少時代に、
わが家では毎日のご飯が白米から玄米に変わりました。
体が弱く、すぐに風邪をひく体質だった私が、
半年で風邪をひかなくなりました。
結核で幾度か血を吐き、
医者から匙を投げられていた父が完治しました。
高血圧だった母は、血圧が安定して元気になりました。
玄米食になってからのわが家は、病院と無縁になりました。
私も二木謙三先生や千島喜久男先生をはじめ、
多くの食養指導者の方とお会いし、知識も多少増えたおかげで、
その後も玄米食を食べ続けています。
玄米食や自然食ももちろん、惜福の工夫ですが、
断食は陰をより強く生じさせる方法。
それを気づかせてくれた本が
『断食療法の科学』甲田光雄・春秋社。
断食は健康管理としてだけでなく、
易経の理解を深めるのにも大変役に立ったと思っています。
☆
【断食スケジュール】
4日ー断食1日目
}恒例お盆一週間断食45回目
10日ー断食7日目、終了(一週間断食)
11日
}回復食 通常は10日間ほどだが今回は短くした。
16日
17日ー東京へ
18日ー致知出版社主催「易経」講座&会食
※断食直後の講座です。↓ 第2講座 ↓
満員御礼。
☆今年も7月から致知出版社主催の易経講座が開催。
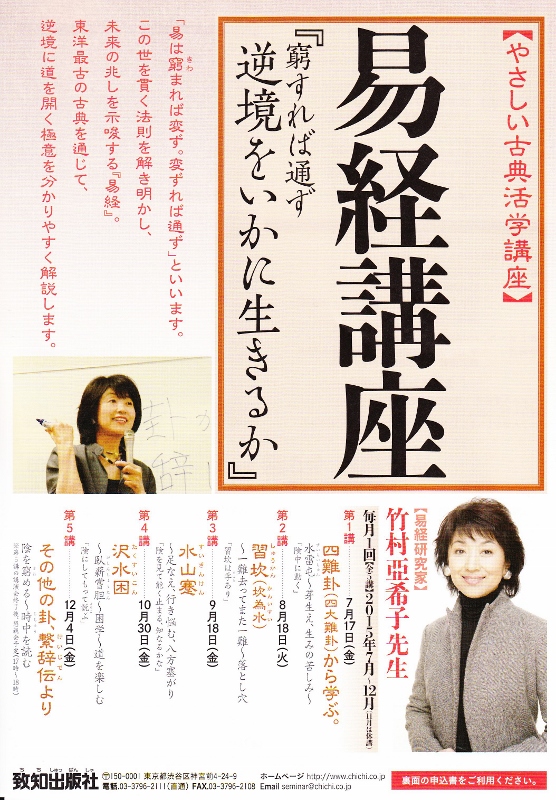
お申し込みは致知出版社まで
http://www.chichi.co.jp/seminar/%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E5%8F%A4%E5%85%B8%E6%B4%BB%E5%AD%A6%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8E%E6%98%93%E7%B5%8C%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8F
雑誌「致知」5月号より
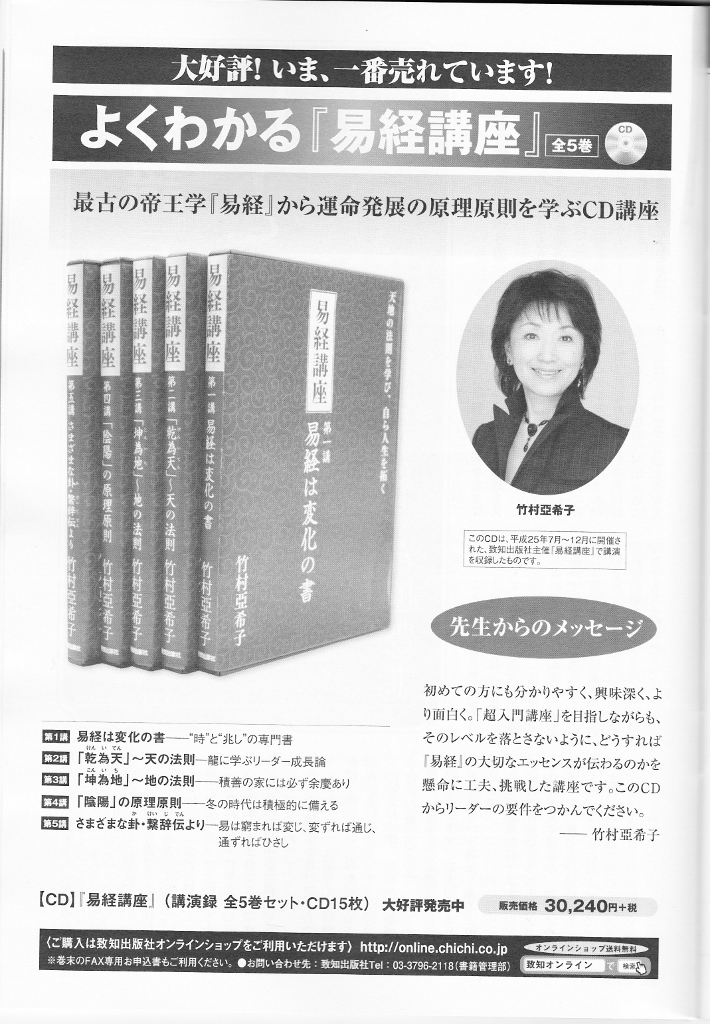
致知出版社主催の易経講座CD・全5巻発売中!
平成25年7月~12月に開催された
致知出版社主催『易経講座』を収録。
